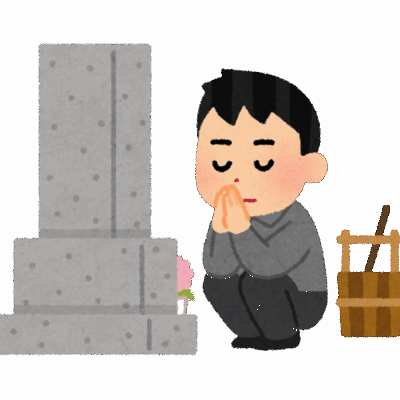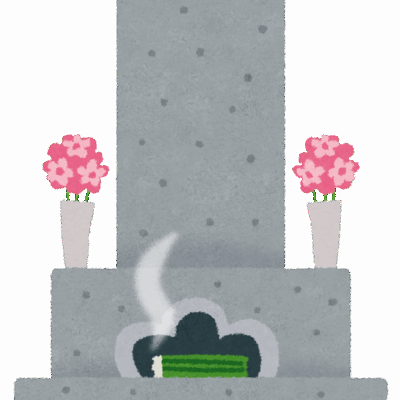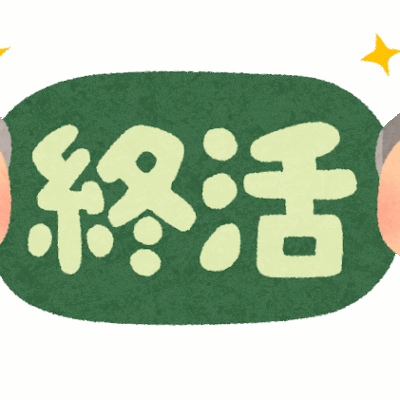徳次郎の奥まった山間の場所にある、立派な墓所の墓じまいのご依頼がありました。
広さとしては12畳分くらいありますでしょうか、歴史を感じさせる大小さまざまなお墓が墓所を囲むように
ずらりと立ち並ぶ姿は圧巻でした。
風化しすぎてご戒名彫が確認できないくらいのお墓がほとんどでしたので、土葬されたお骨は出てこないだ
ろうということだったのですが、予想に反していくつかご遺骨が見つかりました。
今回出てきたご遺骨は、西の杜の合葬墓にご納骨される予定です。
先祖代々のお墓から急に掘り起こされてご遺骨たちもさぞかしびっくりなさったでしょうが、今後もきれい
に整備された合葬墓で、年3回のご供養(春・秋の彼岸、盆)がなされる中お眠りいただけるので、ぜひご
安心いただきたいです。
さて今回出てこられたご遺骨ですが、どのように数えるかご存知ですか?
「柱(はしら)」という単位を聞いたことはありますでしょうか。
日本古来の神様を数える際の単位に由来したものなのですが、故人に敬意を表し神格化する風習があるため
この数え方が用いられたと考えられます。
他に「位」という単位も使われます。
通常等級や順番を表すのによく使用されますが、心霊の宿る場所を表すことから、死者の霊を数えるときにも使われるということです。
私共がよく使う単位といたしましては「霊」でしょうか。
「こちらのお墓は〇霊様お納めできるようになっていますよ」といった具合に使用いたします。
今回の墓じまいで発見されましたご遺骨の内2つは骨壺に納められていたのですが、そうなるとまた呼び名
が変わってまいります。
骨壺は「口(こう)」と数えます。
なので、「骨壺2口が確認された」となります。
「口」はもともと鍋や壷などの器具を数える語です。
なので中身の数え方というより、あくまでもぐるりの骨壺のみを念頭に置いた数え方と言えます。
さてさて、では幽霊になった場合はどうでしょう。
成仏された霊魂を呼ぶ場合は上記のように「柱」や「霊」とお呼びすればいいのですが、「うらめし
や…」と出てこられたいわゆる“おばけ”を数える場合は「人」でいいそうです。
えっ、人に戻っちゃうの?と少し違和感を覚えますが、人間と類似した見た目や行動をとる場合は「人」と
数えることが多いようです。
なので幽霊に限らず、人魚やケンタウロスのような架空の存在も「人」と数えます。
人間は亡くなるといろいろな単位で呼ばれるのですね。
ご遺体のうちは「体」ですもんね。
少し複雑ですが、知っておくとふとしたときに失礼に当たることがないので、ぜひ頭の片隅に入れておいて
いただけたらといいかなと思います。